想定外は想定外だからどうやっても想定できないのですが、どうすれば想定できるでしょう。何となく禅問答のようになってしまいますが、そもそも想定できないというのはどういうことでしょうか。最近起きた災害で想定外の事態に至った感のあるものといえば、2月に首都圏を襲った大雪があります。雪の量自体は確かにこの場所にとっては、またこの季節においては尋常ではないものでしたが、雪そのものは特別なものではありませんし、除雪するための方法や技術には特別な問題があったとは思えません。この事例は、現象が大規模で想定されていない地域に起きてしまったことによると言えそうです。つまり現象そのものはありきたりのものであっても、起きた場所やタイミングが悪かったために、大きな損害になるケースがあります。これは想定できないのでしょうか。
想定といえば地震の被害想定は昔から行われています。かつての地震の被害想定は、そこで起きた最大規模の地震を目安にするのが一般的でした。いわゆる「既往最大」という考え方です。しかしこれでは、もしかするとそこで起こりうる本当の最大地震を見逃してしまうかもしれません。それは地震そのものが、我々人類の生活時間よりも著しく長い間隔で繰り返し発生することも珍しくない事象だからです。人類が登場し、記録が残されているのはせいぜい1000年程度にすぎず、それ以前の地震発生は人の手による記録ではわからないからです。そこで地震の研究者はその地域で過去に起きた地震の痕跡を探して地面を掘ったり(トレンチ調査)、地下を振動で探査したり(爆破探査)、地体構造を研究したり(テクトニクス)、最近ではGPSによる正確な測定などから変化を推定し、僅かな地殻変動も見逃さないようにしたりしています。それでも地震が起きるメカニズムが完全にわかったわけではありませんし、地下構造が見えたとしても、そこで次に起きるイベントが、これまで起きたものと比べて大きいものになるのか、小さいもので終わるのかは、容易にわからないというのが現状です。そこで地震では「どこにでも起こりうるマグニチュード7クラスの地震」なるものが登場し、ターゲットとなる大地震が明確でない日本のかなりの地域で、被害想定の一つの指標になっています。マグニチュード7以上の地震であれば、それなりの変位が地学的調査で発見されている可能性が高いだろうというのも、その理由にはなっていると思われます。
ところが風水害はそこまで想定することがまだ主流ではありません。たとえば先日大雨が降って70名を超す死者を発生させた広島の土砂災害も、あそこで降った大雨を他の地域だったらどうなっただろうという想定は行われません。確かに雨の降り方はその地域の気候的背景があって起きるものですから、広島の雨と同じ振り方が東京でも起きたらという単純な想定は科学的根拠がないのは確かです。東京は広島市のような地形ではありませんし、そもそもあのような降水をもたらすような収束が発生するかどうかはかなり疑問だからです。しかし、昨今あちこちで起きている「局所的だけ出れども非常に強い気象現象」(竜巻や雹などはその典型です)は、これまでの「既往最大」を指標にして防災対策を進めているのでは追い付かない事態ではないかと、防災対策の在り方に疑問を感じさせるに十分なものです。観測記録更新という報告もしょっちゅう起きているような感じをうけますからね。
観測網の整備や衛星からの情報、コンピュータ技術の進展もあって、気象現象はかなり高い精度で数日先の変化を予測できるようになりつつあります。また全球モデルもどんどん研究が進み、近い将来の気候変動も様々な推定が行われるようになりました。とはいえ、いつ(時間の特定)、どこで(場所の特定)、どれくらいの(現象の特定)事態が起きるかを確実に予測するにはまだまだ技術が不足していますし、その間は不確実性はあっても災害の恐れがある場合には積極的に情報を出し、また「空振りをおそれず」に動かなければ被害を減らすことができないのも事実です。いずれ想定外が想定内に収まる日が来ることを祈りながら、いまは想定外に備えた準備も頭の隅に置きながら、できることを着実に進めておきたいところですね。
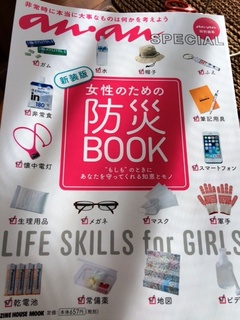
an・anだって防災だ!なかなかよくできていますよ・・・・
an・anだって防災だ!なかなかよくできていますよ・・・・
