東日本大震災から早くも3年3か月が過ぎようとしています。被災地の中でも福島県は放射線量の関係でいまだ帰還できない方々がたくさんいらっしゃいます。このような長期避難、長期被災という構図はこれまでの防災の世界では議論の乏しい分野であったことは確かです。その原因となった東京電力福島第一原子力発電所の事故が実際どのように進展していったのかについては、事故調の報告書を始めいろいろな資料が公開されています。ごく最近、東京新聞原発取材班編の「ビデオは語る-福島原発緊迫の3日間」が刊行され、原発サイトと東電本店、そして政府との生々しいやり取りがある程度わかるようになりました。これは同紙に連載されていた記事を一冊にまとめたもので、連載中私もずっと関心を持ってみていたものでした。
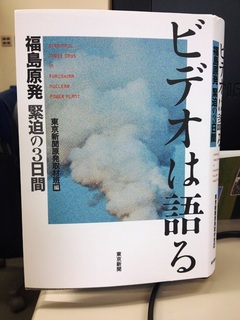
何か問題な事態が起きたときの記録、いわゆる「ログ」をきちんと残すことは危機管理の基本中の基本なのですが、この原発事故についてもビデオ記録という実に有意義な記録が残されていました。ただし、事故直後の約4時間分が録画されていないということと、公開されているのが15日の午前0時過ぎまでに限定されており、一部は音声が抜けている(なぜか画像のみ)こと、また公開されるまでに1年半近くかかった上に市民向けに公開されているのはさらにその一部というのでは、我々が実際の災害対応の経過を理解することはほとんど不可能です。結果的に冷温停止状態なのだから良いではないかと言って片づけてしまうにはあまりに問題が多いように思います。
もちろん記録の中には緊急時の連絡先の電話番号や、担当者の個人名、その他重要な機密事項にあたるものも含まれているかもしれません。しかし事態の切迫性や関係者の緊張度など、動画でなければ感じ取れないことはたくさんあるでしょうし、なにより関係者がどこまでわかって事態の収拾にあたっていたのかを知ることは極めて重要で、未知の危険に対処するあらゆる分野で共通知にすべき情報をたくさん含んでいるはずです。危機管理でこれに勝るテキストはあまりないでしょう。
地震発生当時、第一原発には6400人を超える人たちが作業をしていたそうです。これらの人たちの当時の動きをきちんと整理し、課題があったとしたらどこなのか、今こそ検証すべきです。そのためにも6400人の証言記録こそ、次に公開してほしい記録ですね。
